茨城・月の井酒造店の名杜氏、石川達也さんが目指す「狙わない」酒造りとは【後編】 #職人の手もと
「一見無駄に見えても、残ってきたものには必ず意味がある」。伝統的な酒造りを現代に蘇らせた杜氏(とうじ)が、一見すると非効率に見えるプロセスの意味を語ります。
伝統的な日本酒造りの製法「生酛(きもと)造り」の第一人者である、月の井酒造店の杜氏(とうじ)・石川達也さん。「酒は授かりもの」「酒造りに失敗はない」など、独自の哲学をもって長年酒造りを行ってきました。

1964年広島生まれ。早稲田大学在学中より埼玉県の神亀酒造に入り酒造りを学ぶ。1994年に広島県の竹鶴酒造に移り、1996年より杜氏を務める。2020年より現職。2014年から広島杜氏組合長、2022年からは日本酒造杜氏組合連合会会長も務める。2020年には杜氏として初めて文化庁長官表彰を受ける。
日本酒業界も技術の進化によって効率化されてきましたが、あえて昔ながらの製法である生酛造りにこだわる理由は、結果ではなく体得のプロセスにあると言います。「体得に時間がかかる仕事が廃れつつある」と危機感を募らせる、その胸のうちとは──。
職人は最短距離をいく
江戸時代から続く伝統的な製法である生酛造りは、自然にまかせる部分も大きいので、現代のスタンダードな製法である「速醸(そくじょう)」に比べると手間がかかり、非効率に見えることもあります。
しかし、職人というのは最短距離をいく生き物です。無理と無駄をなくすために試行錯誤するのが職人です。だから、何百年もの時間をかけて出来上がった製法には、ひとつひとつの工程に必ず意味があるはずなのです。
目の前の作業だけ見れば、たしかに非効率な部分もあるかもしれない。けれど長い目で見れば、職人の感覚を養い、ものづくりに必要な知恵がつく。伝統として残ってきた技術には、近視眼的な費用対効果だけでは測れない意味があるのです。
例えば、酒造りの伝統的な道具に「麹蓋(こうじぶた)」があります。麹蓋は小さな容器なので、枚数が必要になり、手入れするにも手間がかかる。だから効率を考えれば、より大きな「麹箱(こうじばこ)」を使った方がいいという考え方もあります。

Asami Saisho/ OTEMOTO
しかも麹蓋は扱うのが難しく、使いこなせるようになるには訓練が必要です。麹箱はやり方さえわかれば使えるようになりますが、麹蓋は頭では理解しても、身体で感覚を掴むのに時間がかかる。マニュアルを読めばすぐ使えるようなものではないので、数年かけて職人を育てなければなりません。
にもかかわらず、江戸時代には麹蓋を使った酒造りがスタンダードでした。職人は無駄を嫌う生き物ですから、当時も箱を大きくしてみたり、扱いやすい形状にしたりと試行錯誤を重ねたはずなんです。でもこの麹蓋がスタンダードなかたちとして受け継がれてきた。
その理由は、当時の職人たちでもはっきりと言語化できた人はいないかもしれません。試行錯誤してみた結果、これが一番しっくりいった。だから長い間残ってきた。けれど伝統を引き継ぐ側の私たちは、先人たちが経験的に辿り着いた製法の裏にある意味を、自分の頭で考えてみる必要があると思います。
「身体で覚える」のが職人の仕事
私なりに考えた麹蓋を使う意義は、麹を身体で覚え、身体で考えられるようになること。麹蓋を使った酒造りはたしかに面倒なことが多いのですが、その面倒な工程こそが、麹を体得するうえで必要不可欠なのです。
麹蓋を使って麹と向き合っていると、言葉では説明できない感覚が養われていきます。
たとえば私が初めて生酛造りに挑戦したとき、従来の造り方に則って途中で酵母を添加したのですが、その直後に「何か余計なことをしてしまった」と直感しました。それ以降は、自分の直感を信じて酵母の添加はせずに造っています。
この直感こそが、身体感覚なのだと思います。しかも生酛造りを長年経験した上での直感ではなく、初挑戦だったにも関わらず、理屈ではなく感覚で「何かがおかしい」と気づいた。それは、身体感覚を重視しながら酒造りに向き合ってきたからこそ培われたものだと思っています。

Asami Saisho/ OTEMOTO
今は麹も機械でつくれるようになり、私たちのように手造りで、しかも面倒な麹蓋を使ってつくるところは少なくなりました。日本酒業界にかぎらず、あらゆる分野においてマニュアル化と機械化が進み、ものづくりにおける身体性が失われていると感じます。
もちろん、麹蓋でつくれば、麹箱や機械でつくるよりいい麹が出来上がるわけではありません。どの方法でつくっても結果が同じならば、誰でもすぐに、しかも安定した品質でつくることができる方が効率的です。
しかしこれを突き詰めていくと、人間はいらなくなってしまいますよね。人間が「職人」として携わる意味がなくなってしまいます。
職人の世界では「手が覚える」という言い方をしますが、ものづくりはプロセスにも意味があるのです。手っ取り早く出来上がればいい、効率的に作れればいいと結果だけを追いかけてしまうと、ものづくりの工程に込められた知恵や精神が失われてしまいます。
機械的につくるだけでは得られない、言語化できない感覚を身体で覚え、その感覚をものづくりに活かしていくことが、職人の存在意義ではないでしょうか。
簡単に辿り着けないからこその喜び
便利になることは、考えずにすむことと表裏一体です。人は不便だから、困難があるから頭と身体を使うんです。その試行錯誤は傍から見ると非効率に映るかもしれませんが、機械に取って代わられることのない価値は、そうやって自分で体得していくことでしかつくられないのではないかと思います。
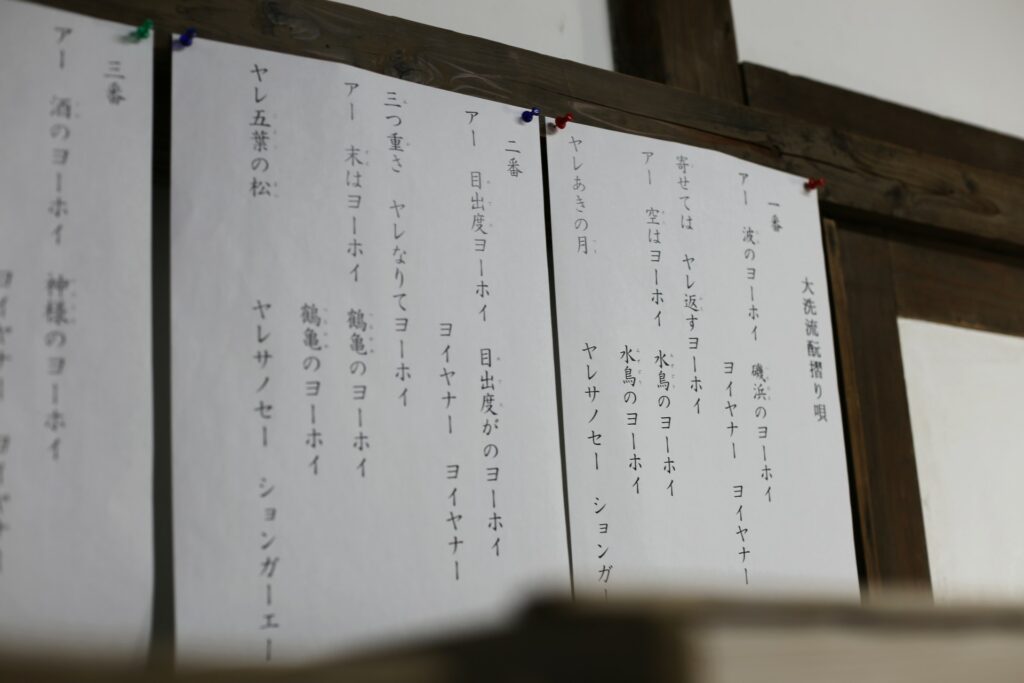
Asami Saisho/ OTEMOTO
そもそも今の便利な暮らしも、過去の積み重ねの上にいるだけで、私たち自身がつくり出したわけではありませんよね。現代人が昔の人よりも頭がよくなったわけではなく、むしろ昔の人の方が不便な中で試行錯誤してきた分、よっぽど偉いと言えるかもしれません。だから今の技術にうぬぼれてはいけない。
とはいえ、昔のやり方をそのまま真似するだけでは意味がありません。自分の技術として体得し、応用していくためには、先人たちが経験則で培ってきたやり方の理屈を自分なりに考える必要があります。
私自身も、まだ生酛造りのすべてがわかっているとは言えません。だから日々酒に向き合いながら調べて考えて、自分なりに伝統技術を理解しようと努めています。
その答えは検索してすぐ出てくるものではないし、時間もかかります。でも、頭ではなく身体感覚も含めて全身で「わかる」瞬間に喜びがあると思うんですよ。天啓が降りてくる快感、とでもいいましょうか。自分で行き着いたからこそ得られるものがあるんです。
しかも、その瞬間がいつくるのかは誰にもわからない。夜中に酒蔵の製麹室で麹の手入れをしていたとき、長年考え続けたテーマの答えが急に降りてきて思わず一人で叫んだこともあります。それくらい、自分で答えに到達した瞬間の喜びは強烈です。

Asami Saisho/ OTEMOTO
だからこの喜びを味わってもらうために、あえて教えずにいることもあります。いじわるで教えないのではなくて、むしろ自分で答えにたどり着いた瞬間の喜びを奪わないためです。
多くの人は、知識や経験というのは右肩上がりに蓄積されていくものだと思っています。でも本当の意味でわかるとか体得する感覚は、ずっとゼロが続いて、ある日急に100になるものです。
考えることは、トンネルを掘りすすむことに似ている気がします。あとどれだけ掘れば終わるのかわからないし、そもそもこの先に光があるのかすらわからない。でも、それでも掘り続けた人だけが、ある瞬間に光に到達する。

最近は生酛造りへの注目が高まっているのもあって、製法を教えてほしいと訪ねてくる杜氏や蔵人も増えました。でもそこでノウハウだけ知って終わりにするのはもったいないですよね。もちろん、ノウハウさえわかれば酒を造ることはできます。でも伝統技術は工程のひとつひとつに意味があり、どれも理にかなっているんです。
その意味を紐解くところに伝統技術の面白さがあり、「わかる」喜びがあるのだと思います。
数十年後も変わらない、芯のあるものづくり
今はどの世界でも、すぐに結果が出ることが求められがちです。検索すればすぐに答えが得られる時代ですし、結果が目に見えるのも早い。だから、目の前の結果に右往左往してしまう。
日本酒の世界では、毎年全国新酒鑑評会が開かれ、そこで評価されるために各酒蔵がしのぎを削っています。しかしその名の通り「新酒」に限定されていますから、今年造った酒の評価をその年にする、ということになります。
しかし、たとえばワインやウイスキーは、造ってすぐではなく数十年後に評価が決まることもありますよね。造ったその年にすぐに評価が下され、目先の結果を出すことばかりに捉われてしまうのはもったいないと思うのです。

味の好みや評価は、あっというまに変化していきます。消費者の好みはもちろんですが、「最高峰の日本酒」を決める全国新酒鑑評会の評価基準ですらも、この数十年の間に何度も変化しています。トレンドや評価基準に合わせることばかり考えてしまうと、どうしても右往左往することになる。これでは芯のあるものづくりはできません。
日本酒も酒造りも、千年以上の歴史を経て培われてきた文化です。だから、先人たちの知恵に学び、その意味を自分なりに解釈して体得していけば、目の前の流行り廃りに左右されることなく、自分たちの芯を持ってものづくりができる。
そしてその豊かな知恵と精神を次世代に引き継いでいくことが、現代の職人である私たちの役目なのではないかと思います。
前編はこちら

前編では、「狙ったら外れる」「酒は授かりもの」など、石川杜氏の酒造りの哲学について伺いました。
連載「職人の手もと」とは
OTEMOTOでは、職人の考え方や哲学を紐解く「職人の手もと」シリーズを連載しています。ものづくりに真摯に向き合う職人たちの姿勢から、日々の仕事や暮らしに生かせる学びをぜひ受け取ってください。
「職人の手もと」取材先を募集しています
OTEMOTOの連載「職人の手もと」では、取材させていただける職人さんの情報を募集しています。自薦他薦は問いません。
職人さんの情報は下記のフォームへご入力ください。





















