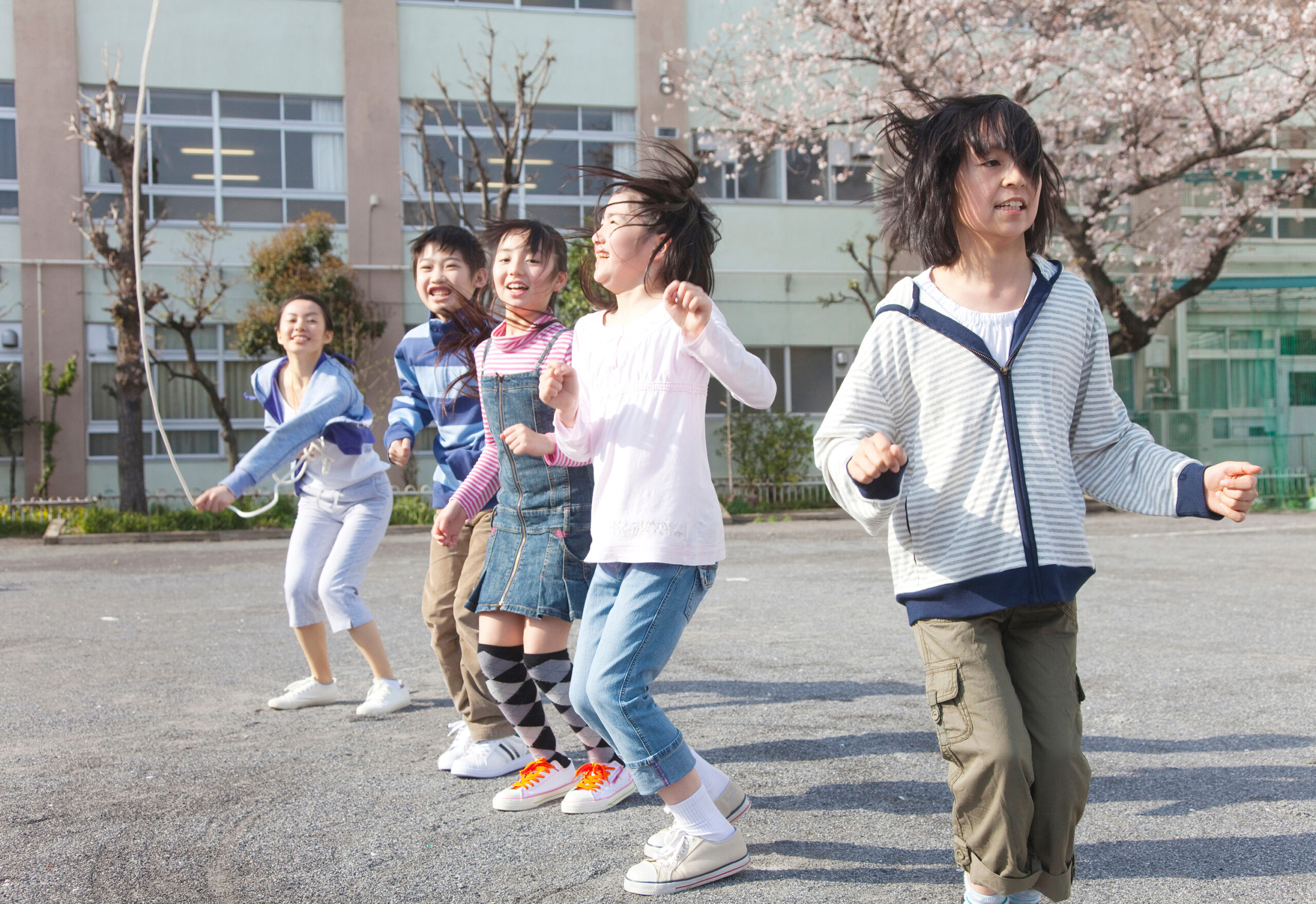運動が苦手な子も、みんなが楽しめる長縄の跳び方を考えてみた。「インクルーシブ教育」のいま
小学校の先生と保護者。距離が近いようでいて、互いを詳しく知る機会はなかなかありません。そこで、お互いの疑問やモヤモヤをぶつけ合ってみる連載を企画。元小学校教員の星野俊樹さんと、小学生のこどもがいる漫画家の田房永子さんの対談の3回目は、特性や背景にかかわらず、すべてのこどもが支援を受けながら学ぶ「インクルーシブ教育」について考えます。
【先生と保護者のチャット01】「保護者会の自己紹介が苦手です」 先生と親、ベストな距離感は?
【先生と保護者のチャット02】選べる制服は「多様性アピール」のため? 教室の中のジェンダーを考える
インクルーシブではない職員室
田房永子 前回のジェンダーの話の続きになりますが、学校案内などのパンフレットを見ていると、最近はさまざまな人種やジェンダーの生徒や、障害のある生徒がモデルとして登場しているように見受けられます。
多様性を尊重していることを学校が表現したい意図はわかりますし、保護者もみんなで順応していっている感覚もあります。
障害や国籍、人種、性別にかかわらず、すべてのこどもが同じ環境で学ぶ「インクルーシブ教育」。なんとなくはわかるのですが、どこか流行語のような感じもして、私としては身をもって理解できているとは言えないんです。実態はどうなのでしょう。

illustration by Eiko Tabusa
星野俊樹 たしかに「インクルーシブ教育」という言葉は、ここ数年で学校の中でもよく聞かれるようになりました。でも、その理念がどれくらい深く浸透しているかというと、僕はまだまだだと感じています。
そもそも学校という場は、家父長制をベースにしていて、そこにはジェンダー規範に基づいた、性別役割分担が埋め込まれていることは前回の対談でお話しました。
【関連記事】選べる制服は「多様性アピール」のため? 教室の中のジェンダーを考える
田房 学校の中で「指導力がある」と評価されがちな「先生像」は、高圧的な態度の男性教員だという話でしたよね。
星野 はい。さらに学校には、育てたい「こども像」もあります。例えば、よく目にする「自ら頑張る」「主体的に取り組む」「たくましい体」といった言葉は、どこか「ひとりでやり抜く力」にばかり重きが置かれているように感じます。もちろん、それは大切な力ではありますが、今の時代には「誰かとつながる力」や「頼る力」も同じくらい大切だと思うんです。

Akiko Kobayashi / OTEMOTO
星野 そして教育現場は「働き方改革」が導入されたとはいえ、教員の労働環境を改善するための根本的な構造改革としてまったく機能していないため、教員たちは「弱さを見せてはいけない」とか「感情は抑えて」「休暇や私生活よりも仕事優先」といった文化の中で働かざるをえないんです。
こうした空気の中で、お互いにケアし合う関係や、ちょっと立ち止まる余白はなかなか生み出せん。こうなってしまうと、現場ではどうしても、合わせることや我慢することが先に来てしまうことが多くなります。
インクルーシブな場所って、本来は"誰もがそのままでいられる空間"であるはずなのに、職員室や教員文化が全然インクルーシブじゃない。だから僕は、まず学校という場の前提や空気そのものを見直すところから始めていかないと、本当の意味でのインクルーシブは実現できないんじゃないかと思っています。
田房 なるほど......。インクルーシブ教育を掲げつつも、集団行動や連帯責任の名残はありますからね。
特に体育の授業では、先生も生徒も当然勝ち負けを気にしますし、運動が得意な人には、苦手な子の気持ちはなかなかわかってもらえませんでした。
みんな楽しめる長縄とは
田房 公立の中学校って、運動会で得点種目として長縄(大縄跳び)をやるところが多いみたいですよね。跳ぶのが苦手で何度もひっかかる子はクラスでお荷物扱いされ、本番では晒し者のようになってしまいます。
星野 長縄をみんなでやることがインクルーシブなのか?という話ですよね。クラスみんなで同じ目標に向かうのはいいですが、ひとりひとりが異なる強みを持っているので、跳ぶのが上手いか下手かだけではなく、それぞれがどんなところを頑張れば輝けるのかを考えたいものです。

Adobe Stock
星野 僕が以前、小学3年生の担任をしたときに、こどもたちから「クラス発表で長縄をやりたい」という意見が出たんです。
その際まず、「そもそもクラス発表でなぜ長縄をやる必要性があるのか」、そして「もしやるのであれば、何を最優先にして長縄をするか」をこどもたちと話し合いました。
「回数も大事だけど、とにかくみんなが楽しめることを大事にしたい」という意見が出たため、長縄の跳び方についてさらに話し合いました。すると、跳び方を全員一律にそろえるのではなく、それぞれの意向や自己決定をふまえ、跳び方を選べるようにすることになりました。「縄を回さないで揺らすだけにしてほしい」という子もいれば、「苦手だけど挑戦したいから回してほしい」という子もいました。
田房 その「誰もが楽しめるような工夫や先生からの語りかけ」がありがたいですね。
長縄が苦手な子がクラスメートから責められるなんて、本来は必要のないことだと思います。もしその子が肩身が狭くて学校や運動会を休んでしまったら、クラスメートも気まずくなる。かといってクラスメートが手助けしようにも、全員参加の得点種目としては限界がある。
結局、苦手で責められている子が、つらくてもちゃんと長縄に参加することでみんなが救われるという歪んだ状況になっているような。
最近では、生徒の希望を聞いて、やりたくない子は不参加も選べるという学校も増えていると聞きます。でもまだ各学校の判断に委ねられているようで、その学校に入ってみないとどんな方針なのかがわからない、というのが現状です。
大人のマイノリティ性を伝える
星野 教員は、ある種の権威や権力を持っていて、僕はそのこと自体は悪いわけではないと思っています。問われるのは、その権力をどう倫理的に使うかということです。立場の弱い人をエンパワーメントするために権力を行使することが大事なのかなと思っています。
長縄をすると決めたときにもう一つ、僕自身の自己開示もしたんです。
「小学生の頃に運動が苦手で、運動が得意な子に責められて傷ついた経験がいまだにトラウマになっている」と打ち明けました。
「だから、クラス発表の長縄が、誰かのトラウマになるような経験になってしまうことだけは、先生として避けたいんだよね。そのためにみんなから知恵を貸してもらいたいし、協力もしてほしい」。そう、こどもたちに伝えました。
こどもたちが多様であるように教員も多様であり、それぞれがさまざまなマイノリティ性を持っています。教員が自分の言葉で語ることで、マイノリティ性が多層的に積み上がり、インクルーシブな学校空間ができるように思います。

Adobe Stock
田房 大人とこどもがそうやって対等に対話ができるのは重要ですね。
星野さんはOTEMOTOのインタビュー記事でこんな話をされてましたよね。児童から「先生、結婚してないの?」と聞かれたときに、忙しくてとっさに冷たい返事をしたけれど、翌日、きちんと理由を伝えて謝った、と。それこそが人間同士のコミュニケーションだと感じました。
【関連記事】上半身裸の騎馬戦という「地獄」に苦しんだ僕は、教師になった
保護者は、学校の様子がわからないだけについ先生をディスりがちですが、国が公教育にお金をかけないことが根本的な要因なのに、現場で努力している先生が矢面に立ってすべての批判を受け止めているケースもあると思います。
以前、授業参観で猛暑の日に体育の授業を見学したときに、30人ほどの生徒を1人の先生が指導していたんです。こどもから聞いていた話では集団行動のルールが厳しすぎると感じていましたが、それだけ厳しく統制しないと命を守れないのだということが現場を見て初めてわかりました。
一方的に批判だけするのではなく、先生たちの努力や工夫、進化しているところはきちんと評価して、課題をともに考えていくことも必要ですよね。
「わが子のため」の葛藤
星野 僕自身、多様性教育を実践するようになったのは、過去に同級生を傷つけたことや抑圧してきた反省からです。ジェンダーやセクシュアリティについて、こどもたちと対話をしながら学んできましたが、正解が見つかっているわけではありません。
保護者も同様に、葛藤を抱えていると感じます。自分たちが受けてきた教育の呪縛や、学歴至上主義の成功体験から逃れることは難しいものです。現行のシステムに違和感を覚えつつも、わが子のこととなるときれいごとではなく、この子の人生をよりよくしたいと望むのは当然ですよね。
田房 まさにモヤモヤしています。なんだかおかしなシステムだなーと思うことがあっても、同時に「わが子をその型に入れなければ」とも考えているので。
星野 教育や社会はショートスパンで見るものではないですが、ロングスパンで見るには覚悟を決めなければならず、個人では限界があります。こどもが成人するまでにはこの社会は変わらないだろうから、我が子だけはしたたかに生き延びてほしいと願う気持ちもよくわかります。教員も保護者も葛藤し続けることしかできません。
であれば、僕たち大人がこどもにできることは、相反する価値の中で引き裂かれるような思い、苦しみ、葛藤を「ないもの」として振る舞うのではなく、ひとりの人間として苦しんでいる生々しい姿を見せることではないでしょうか。
田房 私もそう思います。こどもにとって害のない環境や態度を完璧に提供できるわけがない、ということを前提にしているほうが健全ですよね。
「私たちって、昭和に生まれて平成で育ってきたのに、結構よくやってるじゃん」とほめたい日もたまにありますが、基本的には日々葛藤ですね。
星野 教育の「40年ギャップ」という言葉があります。たいていの大人は自分のこども時代から時計の針が止まっていて、その経験をもとに「大人になってから困らないように」とこどもの将来を妄想しながら教育します。20年前の過去にとらわれながら、20年後の世界を勝手にイメージするから「40年ギャップ」が生まれるという仮説です。
大人がよかれと思ってやっていることで、こどもが置いてけぼりされていないか。そんな視点も常にもっていたいですね。

特集「6歳からのネウボラ」 / OTEMOTO